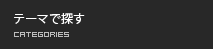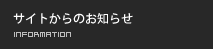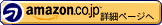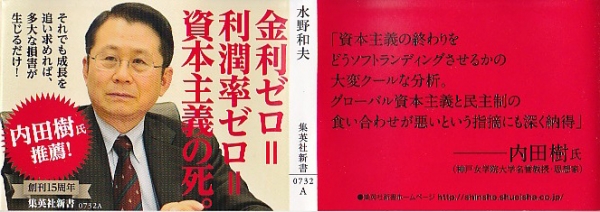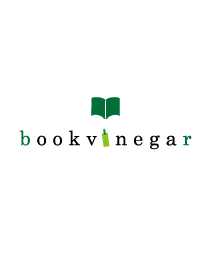
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
資本主義というシステムは崩壊する
ゼロ金利、ゼロ成長、格差拡大。先進国が抱える問題こそが、資本主義というシステムの終焉を意味すると解説する1冊。
■資本主義の限界
資本主義は「中心」と「周辺」から構成され、「周辺」つまり、フロンティアを広げる事によって「中心」が利潤率を高め、資本の自己増殖を推進していくシステムである。
資源を安く手に入れ、効率的に生産した工業製品を高い値段で輸出すれば、高い利潤を得る事ができる。逆に、高い値段で資源を手に入れた場合、価格転嫁ができなければ、利益は薄くなる。交易条件は国民経済を1つの単位として、1製品あたりどれくらいの粗利益を得ているかを表す。1973年の第1次オイル・ショック以降、原油価格の高騰により、交易条件は悪化し続けている。
交易条件が悪化しても、「地理的・物的空間」が拡大してさえいれば、販売個数を増やす事で、利益の総額は増やす事ができる。しかし、1974年以降、実物経済において先進国が高い利潤を得る事ができるフロンティアはほとんど消滅してしまった。「地理的・物的空間」の拡大は困難になり、資源を輸入して工業製品を輸出する先進国の交易条件が悪化し、「地理的・物的空間」に投資をしてもそれに見合うだけのリターンを得る事ができなくなった。つまり、ある一定期間資本を投下し、投下した分以上に利潤を得ていくという資本主義のシステム自体が限界に突き当たったのである。
 超短要約
超短要約
資本主義は「中心」と「周辺」から構成され、「周辺」つまり、フロンティアを広げる事によって「中心」が利潤率を高め、資本の自己増殖を推進していくシステムである。
「アフリカのグローバリゼーション」が叫ばれている現在、地理的な市場拡大は最終局面に入っている。もう地理的なフロンティアは残っていない。また、金融・資本市場を見ても、100万分の1秒、1億分の1秒で取引ができるようなシステム投資をして競争している。この事は「電子・金融空間」の中でも、時間を切り刻み、1億分の1秒単位で投資しなければ利潤をあげる事ができない事を示している。
日本を筆頭にアメリカやユーロ圏でも政策金利は概ねゼロ、10年国債利回りも超低金利となり、その資本の自己増殖が不可能になってきている。資本主義を資本が自己増殖するプロセスであると捉えれば、そのプロセスである資本主義は終わりに近づきつつある。
さらに重要な点は、中間層が資本主義を支持する理由がなくなってきている事である。自分を貧困層に落としてしまうかもしれない資本主義を維持しようというインセンティブがもはや生じないのである。
資本の自己増殖と利潤の極大化を求めるために「周辺」を必要とする資本主義は、いずれ必ず終焉を迎える。現代はもう「周辺」が残されていないからである。「アフリカのグローバリゼーション」という言葉が囁かれるようになった時点で、資本主義が地球上を覆い尽くす日は遠くない。それは地球上のどの場所においても、もはや投資に対してリターンが見込めなくなる事を意味する。すなわち地球上が現在の日本のようにゼロ金利、ゼロ成長、ゼロインフレになる。
 著者 水野 和夫
著者 水野 和夫
1953年生まれ。埼玉大学大学院経済科学研究科 客員教授 元三菱UFJモルガン・スタンレー証券チーフエコノミスト
この本を推薦しているメディア・人物
|
神戸女学院大学名誉教授 内田 樹 |
土井 英司 |
![エコノミスト 2014年 5/20号 [雑誌] エコノミスト 2014年 5/20号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61n8izu8GzL._SL60_.jpg) エコノミスト 2014年 5/20号 [雑誌]
エコノミスト 2014年 5/20号 [雑誌]国学院大学教授 高橋 克秀 |
![週刊 ダイヤモンド 2014年 6/28号 [雑誌]王者タケダ(武田薬品)の暗雲/アドラー「今こそ! 嫌われる勇気」 週刊 ダイヤモンド 2014年 6/28号 [雑誌]王者タケダ(武田薬品)の暗雲/アドラー「今こそ! 嫌われる勇気」](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61orklFxm1L._SL60_.jpg) 週刊 ダイヤモンド 2014年 6/28号 [雑誌]王者タケダ(武田薬品)の暗雲/アドラー「今こそ! 嫌われる勇気」
週刊 ダイヤモンド 2014年 6/28号 [雑誌]王者タケダ(武田薬品)の暗雲/アドラー「今こそ! 嫌われる勇気」作家 佐藤 優 |
 ビジネスパーソンのための「最強の教養書」100 (日経ムック)
ビジネスパーソンのための「最強の教養書」100 (日経ムック) |
![週刊ダイヤモンド2014・2015年12/27・1/3合併号[雑誌] 週刊ダイヤモンド2014・2015年12/27・1/3合併号[雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/619M8IgrZWL._SL60_.jpg) 週刊ダイヤモンド2014・2015年12/27・1/3合併号[雑誌]
週刊ダイヤモンド2014・2015年12/27・1/3合併号[雑誌] |
章の構成 / 読書指針
| 章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| はじめに 資本主義が死ぬとき | p.3 | 1分 |    |
| 第一章 資本主義の延命策でかえって苦しむアメリカ | p.11 | 25分 |      |
| 第二章 新興国の近代化がもたらすパラドックス | p.55 | 27分 |      |
| 第三章 日本の未来をつくる脱成長モデル | p.103 | 19分 |     |
| 第四章 西欧の終焉 | p.137 | 15分 |     |
| 第五章 資本主義はいかにして終わるのか | p.163 | 26分 |      |
| おわりに 豊かさを取り戻すために | p.210 | 3分 |    |
この本に影響を与えている書籍(参考文献、引用等から)
 ユーロ消滅?――ドイツ化するヨーロッパへの警告
ユーロ消滅?――ドイツ化するヨーロッパへの警告[Amazonへ] |
 新装版 ミュージアムの思想
新装版 ミュージアムの思想[Amazonへ] |
 暴走する資本主義
暴走する資本主義[Amazonへ] |
 火山に恋して―ロマンス
火山に恋して―ロマンス[Amazonへ] |
 陸と海と―世界史的一考察
陸と海と―世界史的一考察[Amazonへ] |
 近代世界システムIV―中道自由主義の勝利 1789-1914―
近代世界システムIV―中道自由主義の勝利 1789-1914―[Amazonへ] |
 ヨーロッパとは何か (岩波新書 青版 D-14)
ヨーロッパとは何か (岩波新書 青版 D-14)[Amazonへ] |
 地球システムの崩壊 (新潮選書)
地球システムの崩壊 (新潮選書)[Amazonへ] |