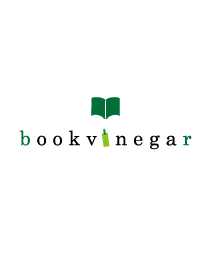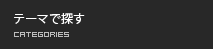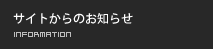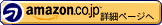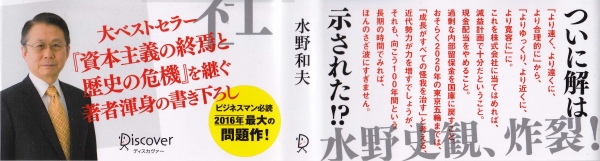これから会社はどこを目指せば良いのか
資本主義による経済成長が限界に達していると説き、21世紀の会社と経済のあり方について考える一冊。
■資本帝国の繁栄
20世紀までの株価は利子率と連動していた。株価は企業業績を反映し、付加価値を分配面からみれば、株価が上昇する時は好況で、雇用者報酬も増加した。1997年までは雇用者報酬は不況でも減少することはなく増加基調にあったので、貯蓄が可能だった。貯蓄の増減は利子率によって決まっていたので、株価と利子率は同じ方向に動いていた。
ところが、20世紀末になると、新自由主義が世界を席巻し、国家は国民に離縁状を叩きつけ、資本と再婚することを選んだ。「資本帝国」においては、雇用者所得を減少させることで株高を維持し、資本の自己増殖に励むことになる。企業の自己資本利益率は、2001年度をボトムに上昇傾向に転じたのに対して、家計の純資産蓄積率は一層低下傾向を強めていった。
株価は過去最高益を更新中の大企業の収益性改善を反映して値上がりする一方、利子率は工場や店舗など過剰資産を反映して、マイナスに転じた。21世紀になると、資本家が、ヒト、モノ、カネを国境を自由に超えて移せる手段を手にしたことで、株価は世界の企業利益を映す鏡となり、利子率は国境で分断された国民の所得を映すようになった。
 超短要約
超短要約
宇宙と地球の空間が「無限」であると、経済成長を優先してきた結果、一人当たりの生活水準は飛躍的に向上した。しかし、20世紀末になると、地球が「有限」になったことが明らかになり、成長は終わった。特に2012年以降、自然利子率がマイナスとなり、潜在成長率もいずれマイナスとなる可能性が高い。
潜在成長率を決めるのは技術進歩、資本量、労働量の3つの要素だが、これらはいずれも既に成長に貢献していない。技術進歩が成長に寄与しなくなったのは、売上増以上に研究開発費などのコストがかかるようになってきたからである。労働量、即ち人口が減少するのは、家計の収入増以上に教育費がかかるようになったからである。資本量は、資本係数が世界一の日本で、これ以上工場を建てたり、M&Aを仕掛けたりして資本を増やせば、将来不良債権になる。
21世紀のシステムは、過去の延長線上ではなく、潜在成長率がゼロであるということを前提に構築していくことが必要である。
 著者 水野 和夫
著者 水野 和夫
1953年生まれ。埼玉大学大学院経済科学研究科 客員教授 元三菱UFJモルガン・スタンレー証券チーフエコノミスト
この本を推薦しているメディア・人物
|
土井 英司 |
![週刊エコノミスト 2016年11月1日号 [雑誌] 週刊エコノミスト 2016年11月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61Mqy%2Bu0dsL._SL60_.jpg) 週刊エコノミスト 2016年11月1日号 [雑誌]
週刊エコノミスト 2016年11月1日号 [雑誌] |
 PRESIDENT (プレジデント) 2016年11/14号「上流老後、下流老後」
PRESIDENT (プレジデント) 2016年11/14号「上流老後、下流老後」 |
章の構成 / 読書指針
| 章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| はしがき | p.1 | 2分 |  |
| 第1章 株高、マイナス利子率は何を意味しているのか? | p.11 | 33分 |      |
| 第2章 株式会社とは何か | p.75 | 33分 |    |
| 第3章 21世紀に株式会社の未来はあるのか | p.139 | 43分 |      |
| あとがき | p.222 | 7分 |    |
この本に影響を与えている書籍(参考文献、引用等から)
 歴史とは何か (岩波新書)
歴史とは何か (岩波新書)[Amazonへ] |
 不確実性の時代 (講談社学術文庫)
不確実性の時代 (講談社学術文庫)[Amazonへ] |
 大停滞
大停滞[Amazonへ] |
 善と悪の経済学
善と悪の経済学[Amazonへ] |
 時間かせぎの資本主義――いつまで危機を先送りできるか
時間かせぎの資本主義――いつまで危機を先送りできるか[Amazonへ] |
 ショック・ドクトリン〈上〉――惨事便乗型資本主義の正体を暴く
ショック・ドクトリン〈上〉――惨事便乗型資本主義の正体を暴く[Amazonへ] |
ユーザーのしおりメモ (0)
- トップページ
- ビジネス書要約・書評
- 株式会社の終焉
- 書評サマリー