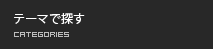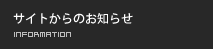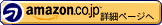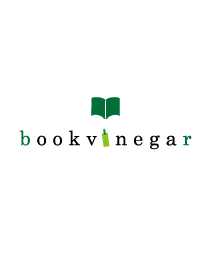
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
量子コンピューターの最前線
光を使った独自の方式により、量子コンピューター開発のトップを走る著者が、量子コンピューターの仕組みや課題を紹介している一冊。
■低エネルギーで動くコンピューター
量子コンピューターは、1980年頃から、その実現可能性について論じられてきた。従来のコンピューターとは異なり、量子コンピューターであれば、計算処理に伴って排出される大量の熱エネルギーを理論上、ゼロにできる。古典コンピューターは、電子回路を使って計算処理を行ったり、メモリーに記録している。その度に、使用された電気エネルギーが熱エネルギーとなって排出されている。電子回路や配線は高温になると動作しなくなる上、高熱により、コアと呼ばれる回路ブロックなどが溶けてしまう。そのため、コアを冷却するのに膨大な量の電気が使われている。既存のスーパー・コンピューターを正常に稼働させるには、原子力発電所1基分以上の電力が必要とされており、その電力の大半が、本来の目的である計算処理ではなく、冷却に使われている。
一般に量子コンピューターと言えば、古典コンピューターに比べて計算処理速度が桁違いに速くなることが最も期待されているが、それ以上に重要なのが、非常に低エネルギーで計算処理ができることである。
 超短要約
超短要約
世界中が量子コンピューター開発バブルに沸き返っている。そのきっかけとなったのは、2011年にカナダのベンチャー企業ディー・ウェーブ・システムズが「世界で初めて量子コンピューターの開発に成功した」と大々的に発表したことである。ロッキード・マーチン社、NASA、グーグルが購入したことを発表した。
しかし、この量子コンピューターは、実は「量子アニーリングマシン」と呼ばれるもので、従来から研究開発が進められてきた汎用型の量子コンピューターとは全く異なる動作原理で動いている。これは、ある特定の問題、いわゆる「組み合わせ最適化問題」の計算処理に特化した専用マシンだ。そのため、これを量子コンピューターと呼んで良いか否かについては、今なお議論の余地がある。
IBMやグーグル、インテル、マイクロソフト、様々なベンチャー企業がこぞって、本来の汎用型の量子コンピューターの研究開発に本腰を入れ始めている。時折、研究成果が発表され、研究開発が順調に進んでいるかのような雰囲気を匂わせているが、課題は山ほどあり、果たして本当に実用化される日はくるのか、その実現性に関してはまだまだ未知数だ。
 著者 古澤 明
著者 古澤 明
1961年生まれ。東京大学大学院工学系研究科 教授 ニコン、東京大学先端科学技術研究センター研究員、カリフォルニア工科大学客員研究員、東京大学大学院工学系研究科助教授を経て、2007年から現職。
この本を推薦しているメディア・人物
|
作家 竹内 薫 |
 週刊東洋経済 2019年3/16号 [雑誌](自動車 乱気流)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51HX4fW96FL._SL60_.jpg) 週刊東洋経済 2019年3/16号 [雑誌](自動車 乱気流)
週刊東洋経済 2019年3/16号 [雑誌](自動車 乱気流) |
 週刊エコノミスト 2019年 4/9号
週刊エコノミスト 2019年 4/9号 |
章の構成 / 読書指針
| 章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 第1章 量子の不可思議な現象 | p.15 | 9分 |    |
| 第2章 量子コンピューターは実現不可能か | p.33 | 13分 |      |
| 第3章 光の可能性と優位性 | p.59 | 13分 |    |
| 第4章 量子テレポーテーションを制する | p.85 | 16分 |    |
| 第5章 難題打開への布石 | p.117 | 15分 |    |
| 第6章 実現へのカウントダウン | p.147 | 21分 |    |
| おわりに | p.188 | 1分 |  |
キーワード
- 量子コンピュータ
-
量子力学的な重ね合わせを用いて並列性を実現するとされるコンピュータ。 量子コンピューターで計算…
この本に影響を与えている書籍(参考文献、引用等から)
 ファインマン計算機科学
ファインマン計算機科学[Amazonへ] |